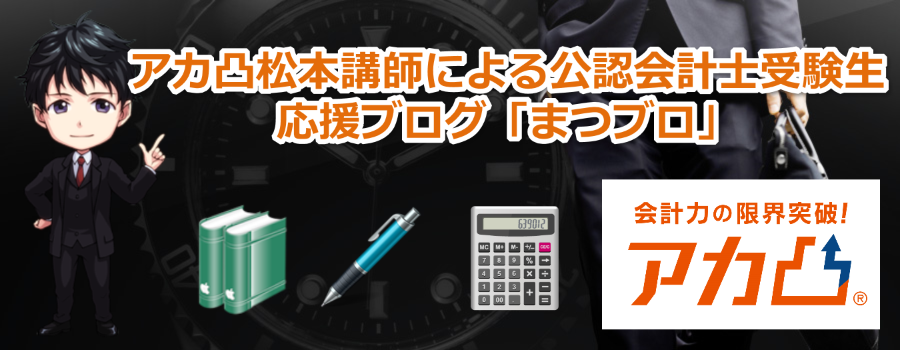論文不合格者の皆さんへ~大きな壁の正体とは? あなたに足りないのは○○感~ver.2.0
どうも、松本です。
論文の合格発表日の翌日よりこの記事の執筆を開始しました。
アカ凸講師として、論文合格発表のあった後にいつも思うことがあります。
どうしても論文の不合格者にその思いの丈を伝えたいので、改めてまつブロをUPすることにしました。
論文の成績通知書をお手元に置いて、静かな環境でご覧下さい。
必ず一人で見て下さい。
不合格という現実を目の当たりにした者にしか伝わらない感情をあなたとシェアしたいと思います。
途中、泣きそうになっても、最後までじっくりと読んで下さい。
あなたに足りないものが明確になるはずです。
本当はアカ凸受講生だけに限定して伝えたい内容でもあります。
でも、論文不合格の辛さを経験している私としては、多くの不合格者に知って欲しい内容であるため、まつブロ内でお伝えすることにしました。
例によって長くなります。(21年12月に追記しましたので、文字数が15,000字を超える超大作になりました。)
今から書き綴る内容は、下記の4つの要件を満たす方に向けてのメッセージです。
①論文不合格者の方が、②成績通知書を手元に置いて、③論文当日の本試験問題を思い出しながら、④辛い気持ちと悔しさを抱えて、読んでもらうこと。
この4要件を満たさない方には、おそらく理解できない文面も多々あるかと思います。
来年の論文合格を勝ち取りたい短答受験生やこれから勉強を本格化する初学者受験生には、不可思議に感じる奇妙な内容ですらあると思います。
「これが、いずれ到達する大きな壁の正体なんだ。」ということを思い思いに感じながら、今後の論文学習に活かして頂ければと思います。
では、始めていきます。
まずはこんなお話から。
昔あるところに貧しい農夫がおりました。
その農夫はガチョウを飼っていました。
ある時、ガチョウは光り輝く黄金のタマゴを産みました。
市場に持っていくとそのタマゴは何と純金だったのです。
黄金のタマゴは、たいそうな高値で売却することができました。
その後もガチョウは毎日1個、黄金のタマゴを産み続けました。
タマゴを売った農夫の暮らしはどんどん豊かになり、やがてお金持ちになりました。
しかし、農夫は1日に1個のタマゴでは満足できなくなっていきました。
次第に「ガチョウの腹の中には黄金が詰まっているに違いない。」と考えるようになりました。
そしてある日、ガチョウの腹を切り裂いて黄金を取り出そうとしました。
しかし、ガチョウの腹の中には黄金などありませんでした。
ガチョウは死んでしまい、農夫は二度と黄金のタマゴを手に入れることができなくなりました。
これは有名なイソップ童話「ガチョウと黄金の卵」です。
大事に育てていれば長期的に利益を得ることが出来たはずなのに、目先の欲に駆られた結果、その利益を生み出す資源まで喪失してしまう可能性がある。
一度に大きな利益を得ようとすると上手くいかないので、長期的な観点から「本当に大切なものは何なのか」を見定めることが必要である。
といった教訓を与えてくれます。
これを会計士の論文試験に当てはめてみます。
大事に育てていれば長期的に利益を得ることが出来たもの=自分で考えて自分の言葉で説明する思考力
目先の欲=答練や模試の得点や順位
その利益を生み出す資源まで喪失=答練を優先し、暗記に走った結果、自分で考えて自分の言葉で説明する思考力の喪失
ふむふむ。
では、次のお話へ。
ある時、北風と太陽が言い争いをしていました。
議題は、「どちらが強いのか」ということ。
話だけでは埒が明かないので、力比べの勝負をすることにしました。
ルールは、「近くを通りかかった旅人の上着を脱がせたほうが勝ち」というものです。
北風は、力いっぱい冷たく強い風を吹いて上着を吹き飛ばそうとします。
しかし、旅人は寒さのあまり、ぶるぶると震え、上着が脱げないようしっかりと押さえてしまい、脱がせることはできませんでした。
次に太陽が、さんさんと光を照らします。
最初は優しいあたたかさで旅人を包んでいましたが、だんだん日差しを強くしていくと、旅人はあまりの暑さに上着を脱いでしまいました。
こうして、勝負は太陽の勝ちとなりました。
これまた有名なイソップ童話「北風と太陽」です。
手っ取り早く乱暴な手段をとった北風よりも、ゆっくりと気長に着実な方法を選んだ太陽のほうが強かったというわけです。
何事も焦らずに、じっくりと取り組むことの大切さを教訓として与えてくれます。
強硬策ではなく、状況によって、臨機応変に対応を変える柔軟性の必要を説いた教訓とも言えます。
北風と太陽を会計士の論文試験に当てはめてみます。
手っ取り早く乱暴な手段をとった北風=軽々と論証例の丸暗記に走る学習をとった不合格者
ゆっくりと気長に着実な方法を選んだ太陽=理解を重視し、必要な部分は記憶に定着した上で、その場に応じて自分の言葉で説明する合格者
さて。
これより本題。
イソップ童話はかく語りき。
上記で紹介したイソップ童話ですが、2つの物語の本質が同じであることに気が付いたでしょうか?
それは、
短絡的かつ近視眼的な結果に終始すると上手くいかない。
長期的な目線を持って、じっくりと時間をかけた取り組みこそが肝要である。
一見すると面倒だと思うことや遠回りと思うことにこそ、本質的な解決策がある。
ということです。
日本語のことわざで言うところの「急いては事を仕損じる」「急がば回れ」にも通ずる、たいへん示唆にとんだ童話です。
では、これらのイソップ童話を踏まえた上で、私が論文不合格者の皆さんへ問いかけます。
問いかけは全部で22問あります。
成績通知書を前にじっくりと考えてみて下さい。
1.学習の中心が答練の準備とその復習に追われていませんでしたか?
2.答練で丸暗記した記述は本試験でその通り展開できましたか?
3.今年の学習方法の継続で来年の本試験に合格できるとの確信が持てますか?
4.本試験で論証の丸暗記を展開しないと合格できないほどの限界を感じましたか?
5.模試や答練よりも簡単で基本的だけど頭を使う問題が多かったのではないでしょうか?
6.難易度の高い問題を解けなくても、得点率には大した影響が及ばないことが理解できますか?
7.短答時点の学力では解けていたのに、論文前に確認しなかったために取りこぼした基礎論点がたくさんあったのではないですか?
8.本当に模試や答練にフルコミット(完全に依拠すること)しないと合格できない試験だと思いますか?
9.壊滅的な出来だと思っていた科目が、実際そこまで悪い順位ではないという事実に気付きましたか?
10.受験生のレベルが、あなたが思っているほど高くないという事実に気付きましたか?
11.暗記だけでは到底太刀打ちできない「その場で考える」ことの重要性に気付きましたか?
12.論文の学習は、考える時間よりも覚える時間の方が多かったのではないですか?
13.配点が10点の記述問題は、10点を取る学習ではなく、満遍なく5点を取る学習の方が成果が出ることに気付きましたか?
14.一言一句に拘る完璧主義の学習が、自らのモチベーションを下げる要因となったことが分かりますか?
15.なぜ、答練や模試にばかり注力し、テキストの論証例や基本問題の反復と定着を怠ったのですか?
16.模試の成績表や順位に何か意味がありましたか?
17.模試の出題と本試験の出題は完全に一致していましたか?
18.落ちたのは、難しい応用問題が解けなかったことに原因があると思いますか?
19.基本的な問題を取りこぼしたことが原因なのではないですか?
20.どうして答練や模試の順位に一喜一憂してしまったのですか?
21.周りの受験生がやっていることが、あなたが勉強する動機付けになっていませんか?
22.論文のための講義を受けても到達できない「何か」の正体が分かりますか?
最後の22の問いかけ以外は、あなた自身で今一度じっくりと考えてみて下さい。
おそらく、8割から9割ぐらいは当てはまる(=思い当たる節がある)のではないかと思っています。
図星でしょ?
プロ講師なんで、受験生の不合格要因ぐらいはとっくの昔に分析済みです。
ここから先は最後の問いかけに対する話を展開していきます。
講義を受けても、答練を受けても、その復習をしても、たどり着けなかった原因は何でしょう?
論文の試験日と、合格発表日をともに経験したことで、ようやく掴める「本試験の正体」
それが、
合格率30%~40%の、その場で考えさせる試験
だということです。
「合格率30%~40%」が持つ意味については後述しますので、まずは「その場で考えさせる試験」の意味から説明します。
合格するためには、「その場」を作って、「自分で思考する訓練」が不可欠なのです。
えっ、「その場」っていうのが答練のことじゃないの?
と思ったあなた。
違います。
厳密に言うと、答練だけではありません。
もっと厳密に言うと、答練に拘る必要もありません。(ここがポイント!)
順を追って説明していきます。まず、
落ちる人の勉強方法は答案の暗記から入ります。
何も考えずに答案を覚える学習は楽だし分かりやすいです。
でも、受かる人は違います。
受かる人の勉強方法は答案の構成から入ります。(具体的なやり方は後述します。)
論点を炙り出して、記述の構成を自分で考える学習をします。
この学習は頭を使うので面倒ですし、分かりにくい部分が多いです。
今まさに私がまつブロの記事を書いているように、真っ白のキャンパスに自分で一から文字を紡ぐ必要があります。
でも、合格する人はその学習を実践しています。
ガチで書く人は「答案」を書いて提出しますが、時間がない人は答案を書かずに「答案構成」だけで済ませてしまいます。
「テキスト」の設例でも「問題集」の問題でも、簡単に答えや解説を見ません。
もっと言うなら、講義に頼りません。
自分で、答案の流れ(テクニカルタームや結論、パラグラフの配置や論理構成の手順など)を白紙の用紙に一から書き出していきます。
だから、「その場」というのは答練の場だけを指すのではなく、「テキスト」や「問題集」を含む広い媒体について、自分で文字を書く訓練の場のすべてを指します。
一度解いた答練の復習も再度、「その場」を作ります。
つまり、教材の本質的な使い方は「テキスト」も「問題集」も「答練」も「模試」も変わらないのです。
これだけだと抽象的ですので、もう少し具体的な事例で説明します。
例えば、企業法について。
テキスト(兼論証問題集)に問題が100問掲載されているとします。
答練と模試が全10回あるとします。
答練と模試は大問が2問なので、全10回×2問=20問しか問題に触れる機会がありません。
一方で、テキストには100問あります。
このテキストをインプットのための教材だと思うのではなく、答練と同じようにアウトプットのための教材として利用するのです。
そうすれば、広く浅く120問の大問にリーチできます。
近年の本試験は昔みたいに大問2問がともに「機関」からの出題ということは少なくなりました。
社債や株式、設立や組織再編などの「機関以外」からの出題が目立つようになりました。
こうなると、20問しかない答練にフルコミットする学習自体が、リスクファクターにすらなり得ます。
楽で明瞭な勉強方法を取る不合格者と面倒で頭を使う勉強方法を取る合格者の違いが、ここにあります。
速攻×即効の論文対策講座でも再三指摘していますが、理論科目において楽で明瞭な勉強方法を取る学習は「経営学の第1問対策」だけです。
経営学は、答案構成がいらない出題形式であることと、短答がなく、知識だけを純粋に問う機会がないことに起因します。
主要科目の理論は絶対に答案の構成から入る訓練が不可欠ですし、これが一番重要です。
答案の構成から入ることが重要な理由は、自分が覚えきれていない部分を炙り出すことが出来るからです。
では、答案の構成とは具体的に何を指すのか?
以下、分かりやすく説明します。
21年11月中旬、R3年度の論文不合格者にある問題集を利用した実験をして頂きました。(勝手に被験者扱いをして申し訳ない。)
問題:実際原価計算制度において予定価格を適用するメリットと留意点について説明しなさい。(解答行数は5行)
いきなり上記の問題を考えて頂きました。
典型論点です。
さぁ、あなたも考えましょう。(ここが重要!!)
(考えて、ポイントを列挙出来た方は引き続き ↓ へGO!)
皆さん、急に出題されたので戸惑いながら「何だっけ、えーっと、、、うーん・・・あれ、確か・・・」みたいな感じで悩み(ここが重要!)、それぞれ口頭で解答して頂きました。
模範解答のポイントを抜き出すと
メリット①:計算の迅速化(実際原価の集計を待つ必要がない。)
メリット②:原価の偶然性の排除(実際価格の季節的な変動による影響を回避できる。)
留意点:差異が多額にならないように予定価格を実際価格に近似させる点に留意
と記載されていました。
実験してみると、メリット①はほとんどの人が解答できていましたが、メリット②は意外と忘れている方が多かったです。
これでいいじゃないですか。
この学習でいいじゃないですか。
悩んだ結果、忘れていたことに気付けたのだから。
論文はこの順番での学習が一番力がつきます。
そして、この問題を私が解くなら、紙やI-Padのメモには下記のように記載します。
メリット①:計算の迅速化
メリット②:原価の正常性
留意点:実際価格に近似
これが「答案の構成」になります。(たったこれだけよ。)
イメージ湧きますでしょうか?
模範解答には、メリット②:原価の偶然性の排除 って記載されていますが、これは別に「原価の正常性の確保」や「原価の季節的変動の排除」でも良いわけです。
しっくりくる言葉で記憶を定着させれば良いのです。(模範解答通りの文言にこだわる必要はありません。)
もっと言いますと、この実験に参加して頂いた方の中には、下記の留意点を説明してくれた人もいました。
留意点:予定価格は標準原価と違って科学的・統計的な裏付けがないため、予定価格設定者の主観性が介入する点に留意が必要
これって大正解じゃないですか!(ちなみに模範解答には記載されていません。)
この記述で行く場合、私なら答案構成には、
留意点:予定価格設定者の主観性
と記載します。
答案を構成する上でのポイントは2つ
1.必ず問題から入ること。
2.専門用語やキーワードを羅列すること
この2点です。
間違っても、模範解答の5行を暗記するようなことは絶対にしてはいけません。
なぜなら、この問題がこの出題形式と解答行数(5行)のまま本試験で出題される可能性は限りなく0に近いからです。
問題:実際原価計算制度において予定価格を適用するメリットと留意点について標準原価との違いに言及しつつ説明しなさい。(解答行数は10行)
だったら、5行で丸暗記した模範解答はもはや模範ではなくなります。
先に言及した、「標準原価には科学的・統計的な裏付けがある。」というのが重要なキーワードに挙がってくるからです。
答案を構成する上で、必ず問題から入ることを推奨する理由は3つあります。
①:短答に合格している時点で、既にその論点は知識として知っているから。
②:「えーと、うーん・・・何だっけ?」という思考訓練自体が本試験と同様の状況だから。
③:問題から入ることではじめて自分に足りないものが何かを知ることができるから。
①については、知っているかどうかが重要で、覚えているかどうかは本試験直前期までは重要ではないです。
忘れていたら覚え直せば良いだけですから。
②については、短答合格時に本試験に類する問題をたくさん解いたように、論文においても論文本試験と同じような状況を作ることが肝要です。
そして、それは必ずしも答練とは限りません。
上記の典型論点などは、理論問題集や論証テキストみたいな名前で記載されているので、そういった媒体でも十分、論文本試験と同じような状況を疑似的かつ自主的に作り上げることが可能です。
先に触れた通り、教材の本質的な使い方は「テキスト」も「問題集」も「答練」も「模試」も変わらないのです。
論文の場合、テキストだからインプット、答練だからアウトプットという訳では必ずしもありません。
③については、いきなり問題から解くことで、「メリット②:原価の偶然性の排除」という視点が欠落していたことに気付けました。
先に論文のインプット講義から入ってこの部分をマーカーしても、「そういえば、短答でやったなー。」ぐらいの感想しか残りません。
演習して、ようやく論点が欠けていたり、暗記すべき事項が不十分だということに気付けるのです。
いきなり演習から入るこの学習法こそ、私が提唱しているアウト⇒イン(アウトプット媒体から、自分に足りないものを特定し、記憶として定着させる。)学習です。
何となく分かってきましたか?
これ、めちゃくちゃ重要なことを指摘していますよ。
論文の勉強方法に自信がない人ほど、「答案の暗記」学習に走りがちです。
なぜなら、その論証パターンを知っていることに安心するからです。
論文の勉強方法に自信がない人ほど、答練や模試にフルコミットする学習に走りがちです。
なぜなら、沢山の受験生が解いている問題を解けば安心するからです。
「あぁ、周りの受験生もやっているから、自分もこれをやっていれば大丈夫だろう。」という思考が形成されがちです。
この点、論文の合格率は30%~40%ですので、裏を返せば不合格率は60%~70%ある訳です。
大多数の受験生と同じやり方だと過半数を超える不合格者組に入る可能性が高くなります。
だから!
論文で安心感を得る学習は、絶対にダメです。
本当に重要なことなので、もう一度繰り返しますよ。
論文で安心感を得る学習は、絶対にダメです。
絶対に、です。
例外なく。
合格する受験生は、テキストや答練を考える素材として使用します。
軽々に論証例の暗記に終始したりしません。
しっかり考えて考えて考えて、模範解答と対比する。
模範解答は一つしか記述していませんが、自分がしっかり考えた論理に筋が通っていれば、次に反復する際も自分の考え方を貫きます。
模範解答に合わせるような学習はしません。
10点満点の答案じゃなくても良いことを、合格者及び合格予定者は知っているからです。
大体、模範解答が一つしかないわけないじゃないですか。
もし模範解答が一つしかないのであれば、公認会計士監査審査会が公表するはずです。
短答では正答が公表されているのに、論文では正答が公表されないのはなぜか?
それは、論文では複数の正答を用意しているからです。
加えて、受験学校の模範解答も、よくよく見れば模範とは言い難い記述も相当程度散見されます。
だから、合格者は、良くも悪くも受験学校を過信していません。
最後は自分と、自分の力が付くと信じる学習を貫徹する。
合格者の学習は、同じ答練を使用する場合でも、不合格者の「安心感」を得る学習とはむしろ正反対です。
あえてこの言葉を使うのであれば、「不安感」を得る学習です。
「うーん、しっかり考えた結果だから、自分の記述で問題ないと思う。模範解答とは異なるけど、大丈夫だと思う。」
「自分の言葉で書いたけど、模範解答と言っていることは大体同じだから、OKだと思う。」
「模試の判定はEランクだけど、ここまでの勉強方法で着実に力が付いているから、このまま進めていこう。」
こういった「確信なき学習」こそが論文の真髄。
だから、同じ媒体を使用していても、力の付き方が全然違います。
安心感を求める不合格者と、不安感を求める合格者。
換言すれば、安心感を感じるのは「逃げ」の学習、不安感を感じるのは「攻め」の学習です。
この言葉も論文の本質をついています。
静かな環境で、ご覧頂いていると思いますので、ここで一つ問題です。
「守り」の学習は、安心感と不安感、どちらを得る学習だと思いますか?
じっくりと考えてみて下さい。
ここを考えないから落ちたんですよ。(手厳しいですけど。)
すぐに答えを伺おうとしないで自分で考えてみて下さい。
不安感が「攻め」の学習なんだったら、安心感は「守り」の学習じゃないの?
これは論外です。
攻めと守りを反転させただけ。
全く思考の痕跡が見られません。
答え。
「守り」の学習は、不安感を得るための学習です。
何かを守ろうとする人は常に「不安感」を有しています。
子供のために働く父親は、常にリストラされないか不安を感じています。
いやいや。
ここを守って凌ぎ切れば、最低ラインを確保できるという安心感が得られるのだから、「守り」の学習は安心感を得るための学習だ。
と思う人もいるかもしれません。
いいえ、これは違います。
「凌ぎ切って、最低ラインを確保する」ためには、どんな論点、どんな問題がきても落ちない答案を書く必要があるのだから、「出来ないなら、出来ないなりに立ち回る」勉強方法を確立する必要があります。
「出来ないなら、出来ないなりに立ち回る」勉強方法は、答案の構成で説明した通り、いきなり問題から入っていくことを習慣化することで身に付けることが可能です。
パーフェクト答案を書くという解決策が現実的ではない以上、「この論点は凌いで守ろう」という学習は、常に不安を感じることになります。
よって、「守り」の学習は、不安感を得るための学習です。
ということは、
安心感を感じるのは「逃げ」の学習、不安感を感じるのは「攻め」と「守り」の学習です。
抽象的ですので、もう少し具体的に説明してみると、下記のようになります。
「うわぁ、難しい応用論点が来た。自分の言葉で書けるところまで書いて(攻め)、部分点を取ろう。(守り)」⇒これが「攻め」と「守り」の学習。
「うわぁ、難しい応用論点が来た。分からないから、論証を後で丸暗記しよう。」⇒これが「逃げ」の学習。
だんだん分かってきましたか?
安心感を感じる勉強方法だと、合格できない理由が。
「分からないから答えから入って」が出来ないんです、本試験では。
一生出来ません。
上述したように、論文の場合は短答と違って、模範解答が開示されませんので、本当の意味での「答え」は闇の中です。
満点答案を書こうとする考え方そのものが、ある種、「天に唾を吐く」ほどの愚行とも言えます。
民「おぉ神よ。我に模範解答を与えて下さいまし。さすれば、答案を書いて差し上げます。」
神「おまえらみたいなもんに、模範なんぞいらん。身の程を知れ、バカタレ。下々なりの考えを示せぃ!裁いてやるわ。」
これが「お上」たる公認会計士監査審査会の見解なのです。
だから、素直に自分の言葉で説明するのが一番シンプルですし、採点官(試験委員)の心象も良いです。
アカ凸の速攻×即効の論文対策講座でも、
「本当に成績の良い人ほど、日によって記述する言葉が変わります。」
「その時に感じた言葉でその時に思ったことを記述すればいいや、ぐらいの気持ちの方が上手くいきます。」
と言及しています。
何度かまつブロでも言及していますが、みんな問題の難易度と合格の難易度を履き違えているんです。
問題は難しいですよ。
でも、合格は難しくないです。
なぜなら、どんなに問題が難しくても上述した通り、所詮は「合格率30%~40%」の試験だからです。
目的は論文試験に合格することであって、難しい問題を解くことではありません。
手段の目的化は本末転倒です。
これが仮に、合格率3%~4%の試験なら、全く様相は異なります。
「難しい問題も解けるようになって下さい。」って私も指摘すると思います。
でも、合格率30%~40%程度なら、半分強(これが偏差値52)で合格なので、みんなが解けない問題は手を付けなくても合格できます。
だから、論文に関しては難しい問題が出ても、本番で見定めて上手く切るという対処が重要なのです。
難しい問題を解くという対処は重要ではありません。
この点、短答に関しては様相が少し異なります。
以前、2019年5月短答で管理会計論の計算問題が、場違いレベルな程にめちゃくちゃな難問ぞろいだったのを受けて、まつブロで涙ながらに抗議をしたことがあります。
2021年5月短答でも、相変わらずの鬼畜難度の問題が出題されています。(試験委員ってバ◯なのかな。)
なぜ、私が憤りを隠せなかったのかというと、誰も出来ない問題なのに6分の1の確率で答えが選択肢にあることを問題視したからです。
これだとただの運否天賦の試験になってしまう。
当日、ラッキーだった人に7点ないし8点が与えられる。
これは絶対におかしい、と。
論文なら難問はほぼ全員が0点。
短答なら難問は正答率16.7%で7点ないし8点。
短答はその日運が良かった人を選別する趣旨の試験ではありません。
だから誰も解けないような難問は絶対に短答で出題してはいけないのです。
これに関しては、「天に唾を吐く」ことを引き続きアカ凸講師として行っていきます。
話が逸れてしまいましたので、元に戻します。
さぁ、話はここからいよいよ核心に迫っていきます。(まだ終わりませんよ。)
論文の合格者が、遡って6月から7月の時(この時点では受験生です。)に、私が「論文の勉強はいかがですか?」
と問いかけると、大抵の方が「全体的にまぁ、ぼちぼちです。」と答えていたことにある時、気付きました。
不合格者は「模試でB判定だったので、順調だと思います。」とか「答練は高得点なので、大丈夫です。」みたいな回答が多かったのです。
もしかして、「全体的にまぁ、ぼちぼちです。」というのは、謙遜でも何でもなく、実際に感じている勉強の感覚なのでは?
と、思うようになりました。
「うーん、しっかり考えた結果だから、自分の記述で問題ないと思う。模範解答とは異なるけど、大丈夫だと思う。」
「自分の言葉で書いたけど、模範解答と言っていることは大体同じだから、OKだと思う。」
「模試の判定はEランクだけど、ここまでの勉強方法で着実に力が付いているから、このまま進めていこう。」
こういった「確信なき学習」こそが論文の真髄。
と上記で示した通り、合格者の勉強は、大体どんな問題が来てもそれなりに点数を取れる学習方法なんだから、日々の勉強に安心感や確信なんて持てるはずがない。
実はこの感覚こそが、論文で一番重要なのです。
繰り返しになりますが、この内容は本当は「アカ凸本編」で言及する予定でした。
めちゃくちゃ重要な感覚だからです。
でも、論文不合格を経験した身としては、やっぱり辛い状況下の方に手を差し伸べたくなるのが、講師の心情なのです。
だから、これまで門外不出だった論文合格者ならではの感覚をまつブロ内でシェアすることに決めました。
この、言葉ではうまく説明できない感覚(「不安感」と称している感覚)を不合格者の皆さんには是非、体得して欲しいのです。
不合格者の多くが思う「安心感を得たい。」という気持ちは大変よく理解できます。
宗教と同じなんです。
不安な人ほど、何かにすがりたいのです。
これで大丈夫だと思いたい、のです。
安心できる状況の中で、落ち着いた気持ちになりたいのです。
でも、ここに心の隙が生じるのです。
正確に言うと、心の弱さが露呈する。
という表現の方が言い得ているかも知れません。
論文は勉強方法を間違わなければ、決して合格は難しくありません。
合格を難しくしているのは、あなた自身の考え方にあります。
不合格によって、更に安心感を求めたくなる気持ちは分かります。
但し、その感情に未来がないことは今回の記事で理解して頂けたはずです。
この安心感やコンフォートゾーンと呼ばれる日常の快適空間から脱却しない限り、ステージは上がりません。
R3年度の論文では会計学で非累加法が出題(キ◯ガイ)され、企業法で金融商品取引法が出題(キチ◯イ)されました。
前年に引き続き、経営学の第1問もヘンな問題(◯チガイ)でした。
出題範囲や領域が拡大しているからこそ、どんな問題が出されてもそれなりに記述するという訓練の重要度が高まっています。
では最後に、冒頭のブログタイトルについての答え合わせをしてみましょう。
・大きな壁の正体はあなた自身の考え方
・あなたに足りないのは不安感
です。
相当本質的なことを言及したので、一回読んだだけで理解できない方は、必ず何度も何度も理解できるまで読み直して下さい。
「分かった!」
と感じるエウレカが起きるまでは、論文の学習を再開しないことをおススメします。
「急いては事を仕損じる」「急がば回れ」だったことをお忘れなく。
注意!
このブログの文脈で言及している不安感というのは、「確信なき学習」のことを指しています。
来年も落ちたらどうしよう、という「心情面での不安感」ではありませんので、悪しからず。
「確信なき学習」を継続していれば、「心情面での不安感」はむしろ緩和・軽減されていきます。
やってみて下さい。
いずれ意味が分かる時が来ますから。
論文の借りは論文で返してやろうじゃありませんか!
この不合格があなたにとって意味あるものになるのか、徒労となるのかはこれからの頑張り次第です。
私は、頑張るあなたを応援し続けます!
長くなりましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。
19年11月17日(21年12月03日追記) 公認会計士 松本 翔
関連ページ
- 第2回ランチ会開催!
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文受験生へのメッセージ音声
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文当日の過ごし方、考え方
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文不合格者へのメッセージ
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- キャリア相談会のお知らせ
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文合格者へのお願い
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文受験相談会のお知らせ
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文当日の心得(動画)
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 論文試験後、必読の2冊!
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 税と非常勤と私
- LEC松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 質的重要性と合格答案
- アカ凸松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」
- 事業部の話をするとしよう
- アカ凸松本講師による公認会計士受験生応援ブログ 「まつブロ」